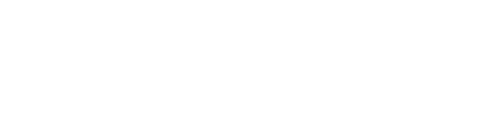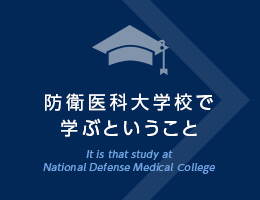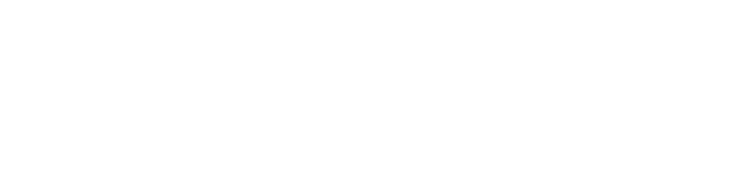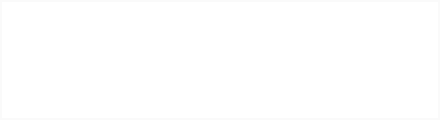小児科学
沿革
防衛医科大学校設立以来、岩波文門教授、吉岡重威教授、関根勇夫教授、野々山恵章教授に続き、今井耕輔教授が令和4年4月に第5代教授に就任し、現在に至っている。近隣の医療機関には多くの元スタッフや卒業生が在籍しており、相互に連絡をとりながら小児医療に従事している。また、本講座からは各地の自衛隊病院の小児科部長のみならず、看護学院長や教育部長を勤める等、指導的立場で自衛隊医療に貢献している卒業生を数多く輩出している。
教育の概要
学生に対する小児科学の系統講義と特別講義は、各分野の担当スタッフが実施している。クリニカル・クラークシップの学生実習は外来実習を主にスタッフが、病棟実習を主に専門研修医とスタッフが、各々担当している。また、小児科は早くから病院外のクリニック実習を取り入れ、主に所沢市内の医療機関の協力を得て、大学病院では経験できない地域の小児医療を実地体験させている。
初任実務研修医の教育については、ローテーション研修医は1ヶ月間という短い期間ではあるが、専門研修医とスタッフの指導の下で主に病棟勤務を行っている。小児科では研修医当直制度を維持しており、病院の小児科当直医と共に夜間や休日の診療を実施することで小児初期救急医療の理解を深めるようにしている。将来小児科医を志望している初任実務研修医については、3~6ヶ月間の初任実務研修期間中に小児科学の各分野を網羅した研修ができるよう、研修を工夫している。
専門研修医については、各種急性疾患への対応をはじめとして、主体的に診療を行うことで、小児科学の各分野を網羅的に研修できるような体制を整備している。同時に、各自が専攻したい分野については、防衛医科大学校病院のみでの研修ではなく、小児病院や特定の分野で先進的な医療を行っている教育医療機関で一定期間部外研修を行うことで、各専門研修医の技量を向上させるのと同時に、習得してきた技術を科にフィードバックしてもらっている。
研究科学生については、各研究科学生は各自の希望に沿って研究テーマを決め、小児科学研究室や研究に必要な設備のある講座や医育機関で研究を行っている。研究の進捗状況は定期的に実施されている検討会で吟味され、これまでの結果やこれからの方向性、また発表内容等について十分な指導を受けている。
看護学科学生に対しても、各分野を専門とするスタッフが講義を実施している。
研究の要約
防衛医科大学校小児科学講座では、研究科(大学院)学生を中心に、一貫して、研究に力を注いでいる。
内分泌・代謝を専門とした吉岡教授の時代には1.5–anhydroglucitolの糖尿病コントロールにおける有用性を証明した。関根教授の時には、川崎病治療におけるウリナスタチンの有効性を初めて示し、以後も病因、病態を含めた研究を、金井講師を中心に継続している。
野々山教授が就任してからは、原発性免疫不全症に関する研究を現在に至るまで行なっている。UNG欠損症による高IgM症候群、PTEN異常による活性化PI3Kδ症候群(APDS)様疾患や、ファンコニ貧血遺伝子異常による分類不能型免疫不全症という疾患概念を提唱したり、GATA2欠損症、APDS1/2等の疾患を本邦で初めて発見する等、目覚しいものがある。また、TRECとKRECを用いた新生児スクリーニング法の開発と有用性を世界で初めて示した。また、野々山教授が代表となって原発性免疫不全症に関する日本免疫不全症研究会(現、日本免疫不全・自己炎症学会)と、中央診断登録システムPIDJレジストリを創設したことにより、日本国内のみならず海外からも免疫不全症関連の検体が解析依頼されてくるようになっている。研究設備に関してはマルチカラー細胞解析装置(FACS)、定量PCR・デジタルPCR装置、次世代遺伝子解析装置(NGS)、デジタル顕微鏡、遺伝子導入機器などを教室内に整備し、多種多様な実験を教室独自で実施可能としている。さらにiPS細胞を用いた、神経、心筋、免疫細胞分化による病態解明を、京都大学iPS研究所をはじめとした国内外の研究機関と密接に連絡・協力を行っており、現在も継続している。
今井教授は、前回在籍時(2004〜2011)、東京医科歯科大学(現、東京科学大学)在任時(2011〜2022)から、野々山教授とともに、免疫不全症の研究、診療にあたり、原発性免疫不全症のみならず脊髄筋萎縮症の新生児スクリーニングの実用化にも尽力し、着任後も新たな治療可能な難病に対する新生児スクリーニング法の開発、社会実装化を行っている。さらに治療法の開発として国立成育医療センター遺伝子細胞治療推進センターと共同で、CRISPRを用いた遺伝子修復療法の社会実装化に向けた研究を行っている。
この他、毛細血管拡張性運動失調症(AT)への放射線障害に対する影響に関する研究や、川崎病の原因、病態、治療法の開発、さらに血液疾患、循環器疾患、神経筋疾患、腎疾患、代謝・内分泌疾患などの幅広い小児疾患に関しても、学内および他の医育機関や研究機関と連携して、研究を行っている。