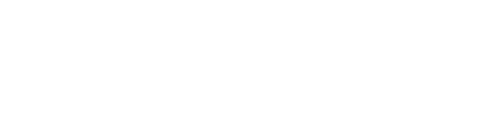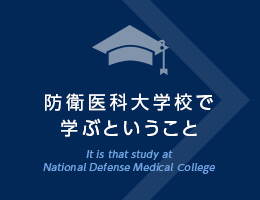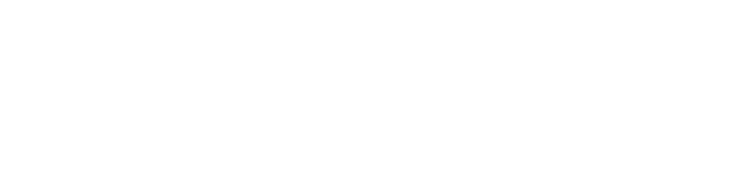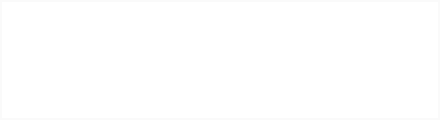保健体育
(1)沿 革
昭和49年4月、防衛大学校から鶴留和男教授(当時は助教授)が着任した。所沢移転後、昭和51年4月から昭和52年3月まで西田明子助教授(東横学園女子短期大学)、昭和52年12月から昭和54年3月まで赤岩岩男教授(武蔵大学)、昭和54年4月から平成5年3月まで神尾正俊教授(武蔵大学)が非常勤講師として授業を担当した。昭和61年5月廣瀬かほる講師が着任する(当時は技官)。鶴留教授の退官後、平成5年1月より平成28年3月まで益子俊志准教授が着任し、授業を担当した。その後、平成31年4月に犬伏拓巳助教が着任した。
所沢移転後、体育施設は体育館、陸上競技場、屋外 バレーコート及びテニスコート、競泳用プール、野球場、ハンドボールコートなどが新設され、施設の充実化が図られたが、平成に入り老朽化が進み、施設の改善・改築が余儀なくされた。平成11年5月には屋外プールの場所に地上4階建ての武道館が完成した。1階が屋内用25m温水プール、3階が柔道、合気道、レスリング、躰道ができる道場、4階が剣道、空手道場である。平成15年2月に、テニスコートもハードコートから人工芝コートに改善された。また、令和4年3月に土のグラウンドから全天候仕様のグラウンドとなり、フィールド内も人工芝へ改修された。これらのことにより体育授業及び学友会活動における学生のスポーツ障害の減少につながった。
更に、令和5年秋季には、新体育館の完成とテニスコート新設予定である。
(2)教育の概要
本校では、体育の重要性を考慮し、平成3年に文部科学省の大学設置基準が改正になり保健体育が必修ではなくなり選択となったが、理論2単位、実技3単位、計5単位を必修とし、授業は第1、2学年とし、これだけでは医師たる幹部自衛官としての体力の維持増進をさせることが難しいため、学友会の運動部活動に積極的に参加するよう指導している。
授業においては球技スポーツを中心とした集団競技を積極的に取り入れ、チームワークの重要性、協調性を養うことに重点を置いて、医師である前に人としての人格を高めることにも教育効果を期待している。女子学生の増加による男女の体格差を考慮しながらも全て一緒に授業に取り組んでいる。また、水泳については夏季定期訓練での遠泳に備え速さより長さを追求してすべての学生が完泳できることを目指している。また、平成21年より体育実技が第3学年にも加わり、上級生としての自覚を涵養できるよう、毎時間リーダーを指名し、リーダーシップの醸成を求めている。理論においてはトレーニングの考え方、安全管理に伴うテーピング実習、スポーツ外傷の予防と応急処置、熱中症の予防と対策等の講義を実施している。
(3)研究の要約
鶴留教授は、防衛医科大学校学生、防衛大学校学生及び一般大学生との運動能力を調査研究した。本校学生は、素質的には優れたものを持っているが成長期における運動不足、また入校後の鍛錬の度合いの低さから防衛大学校学生と比較し持久力が著しく劣弱である。
益子准教授は、ラグビーのスクラム及びタックルにおける障害の研究をした。大学ラグビー選手において頸部障害は、タックル、ラック、スクラムといったプレーにおける衝突場面において多く発生していた。スクラムにおける頸部障害は、対人スクラム練習時の collision 局面において発生する場合が多く、その主な原因は技術不足、疲労、不注意であった。タックルにおける頸部障害は試合時タックルに入る場合に多く発生しており、その原因は技術不足であった。頸部障害の発生状況を考察し、スクラム及びタックルにおける頸部障害を予防するための適切な指導の必要性を示唆した。
また、ラグビー選手の試合または夏季合宿時における身体的・精神的な疲労度の調査研究をした。ラグビー選手の試合前後の POMS と血液生化学値の変動の相関を調べ、更に身体的疲労の評価に有用な血液生化学値について検討した。結果として、ラグビーの試合は筋損傷、体組織蛋白の崩壊をもたらし、ひいては脂質代謝及び免疫機能に何らかの影響を及ぼす可能性がある。また、筋逸脱酵素、脂質代謝関連項目が、身体的な疲労の把握に有用な指標となる可能性が示唆された。また、ラグビー試合翌日の休養法の違いが身体的・精神的コンディションへの及ぼす影響について研究した。試合翌日に完全休養した選手と水中運動1時間行った選手を比較した。生化学値、心理テストの結果有意差はなかった。またラグビー選手のポジション別の疲労度の研究では、激しく身体をぶつけ合う FW 群とランニングが主である BK 群では生化学値に有意差が見られた。FW群は筋逸脱酵素、体組織蛋白の崩壊をもたらし、BK 群では、筋疲労に伴う数値が高かった。このことにより、リコンディションニングを考えるに当たり、単なるラグビー選手という限りではなく、ポジション別に休養・栄養の取り方など考慮することが示唆された。ただ最近のラグビースタイルが大きく変化し、FWもBKも変わらないコンタクト・フィットネスを要求され今後の研究課題である。
廣瀬講師は、岩木健康増進プロジェクト・プロジェクト健診に参加した一般地域住民における過敏性腸症候群(IBS)と呼気中水素・メタン濃度との関係について調査研究した。本研究では、男女別に一般地域住民におけるIBS診断基準を満たす対象者と満たさない対象者での呼気中H₂およびCH₄濃度を検討することで、腸内細菌叢とIBSの関連を検討した結果、女性対象者のIBS-D群でのみ非IBS群と比較して、有意に高値を示した。このことは、H₂産生細菌の増加あるいはその基質の増加によるH₂産生量の増加が女性のIBS-Dの症状を惹起した可能性を示唆していた。今回の結果で、女性のIBS-DのH₂濃度が非IBS群より有意に高く、男性ではそのような傾向が見られなかったことから、IBS-Dには女性ではH₂産生の増加が関与しているが、男性ではその関与がないか小さいと考えられた。