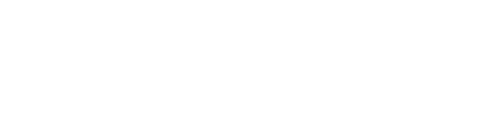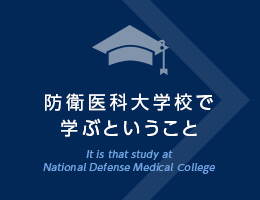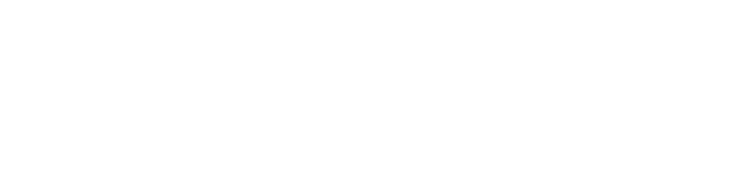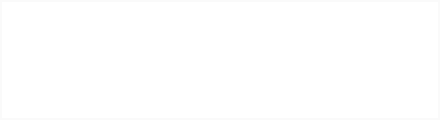分子生体制御学
沿革
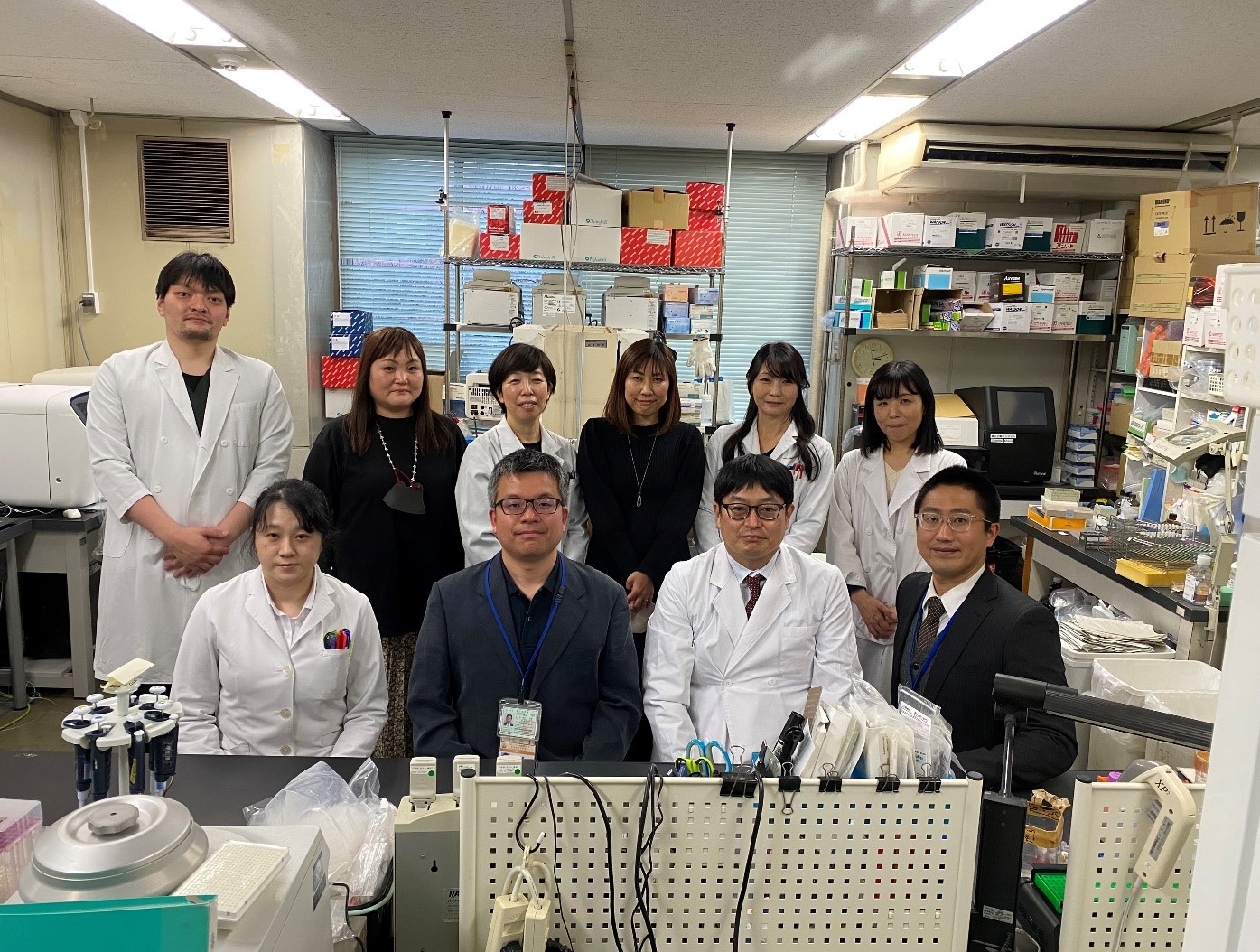
分子生体制御学講座の集合写真 前列左より清水、中山、松尾、豊田
後列左より河村、講座スタッフ(令和5年2月13日撮影)
分子生体制御学講座は、医学科の講座に新しい学問分野への対応を行うことを目的に、「防衛医科大学校の編制等に関する省令」第3条第3項別表第2に新設された(平成18年3月30日)。新設講座の場所は6号館(旧名称:基礎研究棟)の3階であり、旧生理学第一講座の研究室を譲り受ける形でスタートした。これを踏まえ、医官に対する専門研修に関する訓令第9条別表に専門分野に研修科目として分子生体制御学が新設された(平成18年7月28日)。本講座は、“生体を分子レベルで理解し制御に繋げる”という先端基礎医学の時代的ニーズに対応するために、生体や細胞機能の解析・計測・制御を主眼に教育・研究を行い、基礎医学の知見を臨床医学の研究者をはじめとする先生方との共同研究により臨床応用に繋げる橋渡しを行うことを目的に活動してきている。本講座の欧文呼称がDepartment of Integrative Physiology and Bio-Nano Medicineと定められていることからもわかるように、生命の機能を細胞、臓器、個体レベルで理解し、分子生物学やナノテクノロジー等の先端科学技術を駆使して生理学的理解を深める学問分野を担っていることを、国際的にも発信している。
本講座の構成員としては、平成18年4月に、旧生理学第一講座より松尾洋孝(本校医学科16期)が助教(のち講師、准教授)として、生体医工学講座より守本祐司(本校医学科9期)が指定講師(のち講師、准教授)として着任した。平成19年4月には、初代教授として免疫・微生物学講座より四ノ宮成祥(本校医学科4期)が着任した。その後、守本准教授は平成30年4月に生理学講座教授として転出し、四ノ宮教授は令和3年1月に第11代防衛医科大学校長として転出、その後令和4年1月に松尾洋孝が第2代教授として着任した。また、中山昌喜(本校医学科27期)が令和2年3月に講師(のち准教授)として着任したほか、豊田優が令和3年1月に助教(のち学内講師、講師)に、清水聖子が令和5年4月に助教にそれぞれ着任し、現在に至っている。教務職員は、石嶺久子、大澤雄子、保持秀子と引き継がれてきたが、定員削減のためその後は採用されていない。代わって、派遣職員が教務職員相当の事務を担当している。
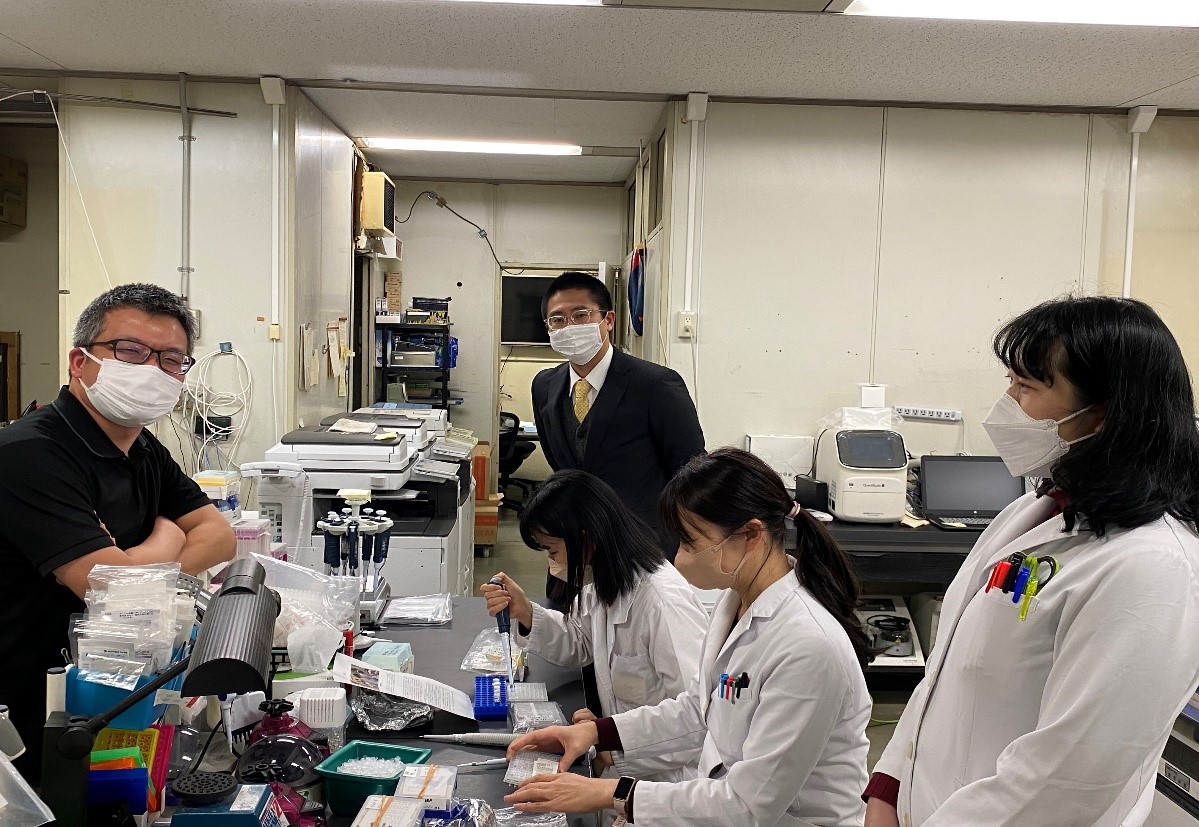
研究室の様子
開設当初の教育活動は医学科学生への授業が主であったが、平成22年には講座初めての専門研修医として中山昌喜医官(現准教授)を受け入れ、平成26年には2人目の専門研修医として千葉俊周(本校医学科26期生)が研修を行った。また、医学研究科学生の受け入れ開始に伴い、本講座最初の研究科学生として平成24年に崎山真幸医官(本校医学科26期生)が入校したのち、平成25年から27年にかけて中山昌喜医官、東野俊英医官(本校医学科29期生)、川口真医官(本校医学科29期生;泌尿器科学講座所属)を受け入れた。現在は河村優輔医官(本校医学科34期生)が入校し、研究に取り組んでいる。
教育の概要
本講座が主担当として行っている科目は、第2学年(令和3年度までは第3学年)に対する機能分子生体制御学である。全般的な目標として、①生命現象である生体制御の仕組みを分子の観点から解析し基礎医学・臨床医学の両面に応用するための基本的な考え方を理解する、②近年の医学・生命科学技術進歩のため従来の分類では領域を設定しにくいテーマについて多角的な面から勉学できる素地を養う、③医学・生命科学に対する探究心を養い自ら進んで勉学する姿勢を身に付ける、の3つを掲げて教育に当たっている。
教育の特徴のひとつは、班ごとに与えられた課題について模擬的に学会形式で口頭発表をさせる授業方法にある。(表1)また、教育の一部は学内公開授業とするなど、基礎医学の基本を知りたい学生(看護科学生、医学研究科学生を含む)はもちろん、聴講を希望する教官等にも広く公開している。さらに、新家一男氏(産業技術総合研究所)を非常勤講師として招聘し、新薬探索に関する講義を行っている。
表1 機能分子生体制御学(第2学年)における学生発表に対する教育内容の例
・課題に対する口頭発表の指導
2)収集した文献における重要点の読解
3)発表時間に応じた目的課題についての適切なスライド資料の作成
4)スライド資料を用いて目的課題を制限時間内にわかりやすく説明
・課題の発表に関連した学内公開授業の例
2)示説(ポスター)発表の方法について
3)医学論文の読み方、探し方について
本講座が多様な役割を担っていることから、種々の学年の教科に対する教育の分担並びに支援も行っている。
第1学年の導入時期に行う医学概論では、基礎医学の面白さについての講義を行っている。
生理学についても講義による医学科および看護学科学生の教育の支援を行っているほか、物質輸送実習を担当している。学生はこの実習で、自ら蓄尿や一時尿といった検体の採取を実施している。さらに、DNAを抽出し多型解析し、検査データと突合させその結果を解釈するという「ゲノム個別化医療・予防」に触れる先進的な実習を経験する。学生はこの実習により、医師としての自覚、受検する患者の立場の経験、そして先進医療の実践という各種の素養を涵養することになる。
専門研修を受け入れる際には、分子生体制御学に関連する日本国内学会での発表のみならず国際学会での発表機会を設け、日本語及び英語での発表能力の向上に努めることとしている。また、一流国際科学誌に筆頭著者として論文掲載することを目指している。さらには、防衛医学先端研究・防衛医学基盤研究をはじめとする種々の研究の枠組みに積極的に参加するとともに、その他の部内における研究開発や研究技術支援にも可能な限り貢献することを理念として掲げている。本講座における具体的な専門研修カリキュラムは、表2に示すとおりである。
表2 分子生体制御学講座 専門研修カリキュラム
| 研修期間 | 到達目標 | 研修方法 |
| 1年目 | 分子生物学、機能分子医学等の研究に必要な基礎的考え方を身につけ、合わせて研究に必要な技能を習得する。腫瘍や代謝疾患の原因となる種々の生理活性蛋白分子について、遺伝子解析、細胞機能解析、動物モデルの解析等が可能となるように努める。特に、研究テーマについての論理的思考構築を重視し、研究結果の客観評価能力や研究内容についての発表(プレゼンテーション)能力を高める。また、戦傷・災害医療と基礎研究との接点を考え、これらについての研修機会を持つように努める。 | 基礎的な分子生物学的手技を習得し、実験研究の進め方について研修する。特に、生理活性蛋白分子の遺伝子解析においてはPCR、シークエンス、遺伝子クローニング技術などの基本操作を、細胞機能解析においては細胞培養、フローサイトメトリー、Western blotなどの基本技術を、動物モデルの解析においては飼育管理、交配、遺伝子型解析、臓器摘出、組織病理評価などの技術を身につける。研究テーマの論理性や結果の適切な評価について、講座におけるセミナー等を通して発表する技術を身につける。また、学会発表や論文作成を通して、研究者として必要な知識の修得に当るとともに、論理性のある結果解釈や発表方法の修得に向けて講座員の指導を受ける。また、病院での臨床研修の場や有事災害の訓練を通して、戦傷・災害医療に対する素養を身につける。 |
| 2年目 | 生理活性蛋白分子の解析技術を向上し、他講座等との学術的連携を介した臨床医学への応用研究(トランスレーショナル・リサーチ)の可能性を追究する。研究結果の客観評価能力を更に高め、口頭発表のみならず論理的構築に基づいた論文作成が可能となるよう努力する。研究の目的や意義が十分説明できるようになるとともに、研究計画の立案や期待される結果の予測が自立的にできるレベルに到達することを目標とする。さらに、研究内容を戦傷・災害医療などに応用できるよう実践的な面についても考察する。 | 1年目に修得した研究手技を更に充実させるとともに、セミナーや講座員の指導を通して実験の目的に合致した研究手法が選定できる能力を養う。トランスレーショナル・リサーチ実践のため、他講座との討論に積極的に参加し、計画・立案の段階から研究内容の企画に加わる機会を設ける。講座におけるセミナーや学会発表で得られた議論を元に、論文作成(特に英文論文)を自立的に行う。さらに、種々の学術発表で得られた成果を発展させて、新たな研究テーマの企画・立案を行う。戦傷・災害医療に対する研修等を通して基礎研究を臨床に役立てる手段について学ぶ。 |
一方、研究科学生に対する教育プログラムとして表3に掲げる項目を設定し、所定の期間に最新知識の学習や技術の習得並びに有意義な研究活動が展開できるよう体制を整えている。
表3 分子生体制御学 研究科授業要目
| 専攻分野 | 授業科目 | 授業目的 | 授業要目 |
|
1 総合基礎医学群 (1)総合生理学系 分子生体制御学 |
分子生体医学 |
遺伝病から多因子疾患までの遺伝的背景に関わる分子病態生理学、具体的な遺伝子解析手法を含む分子遺伝疫学、ならびにビッグデータの取り扱いとその解析手法等の教育を通じて、生体の仕組みや多様な疾患をDNA・RNAレベルから考え、臨床病理の理解につなげるための基礎的知識と研究能力を涵養させる。 また、本領域を通して、自衛隊衛生や国際貢献活動の基盤となる基礎医学的事項について、自ら企画・実行できる研究能力を習得させる。 |
|
| 分子機能制御医学 | 膜輸送体等の生理活性分子の構造・機能やその物質輸送の病態生理学意義を中心とした膜輸送体等の分子生理学の基礎、悪性腫瘍に関する分子生物学的理解、および関連する細胞分子生物学的手法等に関する教育を通じて、生体の仕組みや多様な疾患をタンパク質レベルでとらえ、分子病態の理解につなげるためのトランスレーショナル・リサーチの基礎的知識と研究能力を涵養させる。 |
|
研究の要約
創設から17年を経て、本校におけるトランスレーショナル・リサーチや基礎系講座の学術的ハブ機能の担い手としての活発な研究活動を展開している。
現在、本講座で行われている研究のメインテーマの一つは尿酸を対象としたゲノム医学研究と分子疫学研究である。痛風・高尿酸血症は生活習慣病として有名である一方で、遺伝性疾患である腎性低尿酸血症は希少疾患であるものの、例外的に日本人には比較的多くみられる疾患である。腎性低尿酸血症の合併症である運動後急性腎障害は若年男性に好発することから新入隊員の初期課程の脱落につながるなど、自衛隊衛生においてしばしば問題となる。このような経緯もあり、ヒトの血清尿酸値・尿酸動態に強く影響する代表的な3つの輸送体(トランスポーター)は、いずれも自衛隊衛生の貢献により同定されている。すなわち、腎性低尿酸血症1型の原因遺伝子であるURAT1/SLC22A12の発見(陸上自衛隊熊本病院の症例から; Kikuchi Y, et al. Clin. Nephrol. 2000; Enomoto A, et al. Nature. 2002)、腎性低尿酸血症2型の原因遺伝子であるGLUT9/SLC2A9の同定(海上自衛隊健康診断データベースの解析から; Matsuo H, et al. Am. J. Hum. Genet. 2008)、生活習慣病である痛風・高尿酸血症の主要な原因遺伝子であるABCG2/BCRPの探索(航空自衛隊下甑島分屯基地医務室で収集された検体・健診情報から; Matsuo H, et al. Sci. Transl. Med. 2009)という貢献である。近年ではURAT1選択的阻害薬ドチヌラド(ユリス®)などが上市され、また、世界初の『腎性低尿酸血症診療ガイドライン』は四ノ宮成祥教授が委員長となって策定し英語版(Nakayama A, et al. Hum. Cell. 2019)も含めて無料公開されるなど、自衛隊衛生発の成果は広く世界に活用されるスピンアウトをもたらしている。
現在、痛風・尿酸関係の国際コンソーシアムの一拠点として防衛医大は世界をリードしている。他の大学や研究機関をはじめ、多くの学内の講座と連携しながら、また学外の部隊医官の協力・支援をいただきながら、遺伝子解析、分子機能・局在解析をはじめ、予防医学や臨床医学、看護研究まで広く学際的に融合した分子遺伝疫学研究を行い、ゲノム個別化医療・予防に関する先進的な研究を進展させている。
前述の海上自衛隊の健康診断データベースは、現在では大規模疫学研究に活用可能な先進的なシステムとなっている。また、自衛隊中央病院において実施されている50歳検診は、比較的均一な生活背景を持つ集団における横断的な調査が可能な集団である。このような自衛隊衛生に特徴的な、「ビッグデータ」や「コホート集団」ともいえる環境の構築は研究の追い風となってきた。さらに、令和4年末に策定された防衛3文書(『国家安全保障戦略』『国家防衛戦略』及び『防衛力整備計画』)における「衛生機能の変革」では「各自衛隊で共通する衛生機能等を一元化して統合的な運用を推進する」「戦傷医療能力向上のための抜本的改革を推進する」「隊員の身体歴情報を電子化し、各隊員の医療情報を速やかに検索・閲覧できる態勢を整える」「防衛医科大学校において(中略)戦傷医療対処能力向上を始めとした教育研究の強化を進める」と明記されており、今後もさらなる体制の構築・強化が期待され、隊員の健康管理のみならず持続性・強靭性の向上に有用な研究成果が得られやすくなることも考えられる。現在、防衛医科大学校における研究プロジェクトのひとつとして「バイオ・ゲノムバンクプロジェクト」(自衛隊バイオバンク)が設定され、本省の衛生機能強化委員会でも紹介されている。自衛隊バイオバンクが、ゲノムデータのほか病院や部隊から得られる試料・検体を交えた疾患バイオバンクを含む形として、世界に冠たる研究基盤となることを期待してやまない。
<研究成果>・・・過去10年間(平成24年以降)の業績から抜粋
- Y. Toyoda et al., SNP-based heritability estimates of gout and its subtypes determined by genome-wide association studies of clinically defined gout. Rheumatology (Oxford). 62(5):e144-e146, 2023.
- N. A. Sumpter et al., Association of gout polygenic risk score with age at disease onset and tophaceous disease in European and Polynesian men with gout. Arthritis Rheumatol. 75, 816-825, 2023.
- Y. Toyoda et al., Vitamin C transporter SVCT1 serves a physiological role as a urate importer: functional analyses and in vivo investigations. Pflugers Arch. 475(4):489-504, 2023.
- Y. Ohashi et al., Urate transporter ABCG2 function and asymptomatic hyperuricemia: a retrospective cohort study of CKD progression. Am. J. Kidney Dis. 81(2):134-144.e1, 2023.
- T. Fukushima et al., Clinical significance of prediabetes, undiagnosed diabetes and diagnosed diabetes on critical outcomes in COVID-19: Integrative analysis from the Japan COVID-19 task force. Diabetes Obes. Metab. 25, 144-55. 2023.
- T. Fukushima et al., Clinical significance of pre-diabetes, undiagnosed diabetes, and diagnosed diabetes on clinical outcomes in COVID-19: Integrative analysis from the Japan COVID-19 Task Force. Diabetes Obes. Metab. 25, 144-155. 2023.
- P. E. Sugier et al., Investigation of shared genetic risk factors between parkinson's disease and cancers. Mov. Disord. 38, 604-615. 2023.
- Y. Pan et al., Dasatinib suppresses particulate-induced pyroptosis and acute lung inflammation. Front. Pharmacol. 14 (2023).
- H. Namkoong et al., DOCK2 is involved in the host genetics and biology of severe COVID-19. Nature 609, 754-60. 2022.
- Y. Toyoda et al., Genome-wide meta-analysis between renal overload type and renal underexcretion type of clinically defined gout in Japanese populations. Mol. Genet. Metab. 136, 186-9. 2022.
- Y. Toyoda et al., OAT10/SLC22A13 acts as a renal urate re-absorber: clinico-genetic and functional analyses with pharmacological impacts. Front. Pharmacol. 13, 842717. 2022.
- Y. Shirai et al., Coffee consumption reduces gout risk independently of serum uric acid levels: mendelian randomization analyses across ancestry populations. ACR Open Rheumatol. 4, 534-9. 2022.
- A. Nakayama et al., Genetic epidemiological analysis of hypouricaemia from 4993 Japanese on non-functional variants of URAT1/SLC22A12 gene. Rheumatology (Oxford). 61, 1276-81. 2022.
- Y. Matsui et al., Nanaomycin E inhibits NLRP3 inflammasome activation by preventing mitochondrial dysfunction. Int. Immunol. 34, 505-18. 2022.
- H. Liu et al., Polygenic Resilience Modulates the Penetrance of Parkinson Disease Genetic Risk Factors. Ann. Neurol. 92, 270-8. 2022.
- K. Ikoma et al., Oridonin suppresses particulate-induced NLRP3-independent IL-1alpha release to prevent crystallopathy in the lung. Int. Immunol. 34, 493-504. 2022.
- C. Domenighetti et al., Mendelian randomisation study of smoking, alcohol, and coffee drinking in relation to Parkinson's disease. J. Parkinsons Dis. 12, 267-82. 2022.
- C. Domenighetti et al., Dairy intake and Parkinson's disease: a Mendelian randomization study. Mov. Disord. 37, 857-64. 2022.
- C. Domenighetti et al., The interaction between HLA-DRB1 and smoking in Parkinson's disease Revisited. Mov. Disord. 37, 1929-7. 2022.
- S. J. Chang et al., A meta-analysis of genome-wide association studies using Japanese and Taiwanese has revealed novel loci associated with gout susceptibility. Hum. Cell 35, 767-70. 2022.
- 中杤昌弘, 中山昌喜, 松尾洋孝, 血清尿酸値の個人差は遺伝要因によってどの程度説明できるのか?. 痛風と尿酸・核酸 45, 1-11. 2021.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, in ヒトゲノム事典, 井ノ上逸朗 et al., 編集. (一色出版, 東京, 2021), chap. 20, pp. 288-91.
- 河村優輔, 中山昌喜, 松尾洋孝, 【疾患ゲノム研究の最前線】痛風のゲノム研究最前線. BIO Clinica 36, 413-8. 2021.
- Y. Toyoda et al., Substantial anti-gout effect conferred by common and rare dysfunctional variants of URAT1/SLC22A12. Rheumatology (Oxford). 60, 5224-32. 2021.
- H. Tanaka et al., Clinical characteristics of patients with coronavirus disease (COVID-19): preliminary baseline report of Japan COVID-19 Task Force, a nation-wide consortium to investigate host genetics of COVID-19. Int. J. Infect. Dis. 113, 74-81. 2021.
- M. Sakiyama et al., Porphyrin accumulation in humans with common dysfunctional variants of ABCG2, a porphyrin transporter: potential association with acquired photosensitivity. Hum. Cell 34, 1082-6. 2021.
- M. Ogura et al., Increase of serum uric acid levels associated with APOE epsilon2 haplotype: a clinico-genetic investigation and in vivo approach. Hum. Cell 34, 1727-33. 2021.
- A. Nakayama et al., First clinical practice guideline for renal hypouricaemia: a rare disorder that aided the development of urate-lowering drugs for gout. Rheumatology (Oxford) 60, 3961-3. 2021.
- M. Nakatochi et al., An X chromosome-wide meta-analysis based on Japanese cohorts revealed that non-autosomal variations are associated with serum urate. Rheumatology (Oxford). 2021.
- Y. Kawamura et al., A proposal for practical diagnosis of renal hypouricemia: evidenced from genetic studies of nonfunctional variants of URAT1/SLC22A12 among 30,685 Japanese individuals. Biomedicines 9, 1012. 2021.
- M. Kawaguchi et al., Both variants of A1CF and BAZ1B genes are associated with gout susceptibility: a replication study and meta-analysis in a Japanese population. Hum. Cell 34, 293-9. 2021.
- 中嶌真由子, 中山昌喜, 松尾洋孝, 【尿酸に影響する遺伝性代謝異常、最近の進展】低尿酸血症 腎性低尿酸血症. 高尿酸血症と痛風 28, 59-64. 2020.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, 四ノ宮成祥, 【腎臓と運動・スポーツ】運動後急性腎不全 腎性低尿酸血症による腎障害. 腎と透析 88, 533-7. 2020.
- 中山昌喜, 「医務室でのレセプト情報処理業務を効率化するファイルの開発」および「医務室での使用に適した医療費計算ファイルの開発(続報)」. 防衛衛生 67, 1-11. 2020.
- 河村優輔, 松尾洋孝, 清水聖子, 中山昌喜, 四ノ宮成祥, 【症例で学ぶ!腎泌尿器診療ガイドラインの使い方】(第8章)代謝性疾患 腎性低尿酸血症 モデル症例とピットフォール. 腎と透析 88, 377-83. 2020.
- S. Takihata et al., The influence of a noisy environment on hearing impairment and tinnitus: The hearing outcomes of 50-year-old male Japan ground self-defense force personnel. Auris. Nasus. Larynx 47, 931-7. 2020.
- A. Nakayama et al., Subtype-specific gout susceptibility loci and enrichment of selection pressure on ABCG2 and ALDH2 identified by subtype genome-wide meta-analyses of clinically defined gout patients. Ann. Rheum. Dis. 79, 657-65. 2020.
- A. Nakashima et al., Dysfunctional ABCG2 gene polymorphisms are associated with serum uric acid levels and all-cause mortality in hemodialysis patients. Hum. Cell 33, 559-68. 2020.
- Y. Kawamura et al., Identification of a dysfunctional splicing mutation in the SLC22A12/URAT1 gene causing renal hypouricaemia type 1: a report on two families. Rheumatology (Oxford) 59, 3988-90. 2020.
- T. Higashino et al., Dysfunctional missense variant of OAT10/SLC22A13 decreases gout risk and serum uric acid levels. Ann. Rheum. Dis. 79, 164-6. 2020.
- A. Akashi et al., A common variant of LDL receptor related protein 2 (LRP2) gene is associated with gout susceptibility: a meta-analysis in a Japanese population. Hum. Cell 33, 303-7. 2020.
- Y. Toyoda et al., Identification of GLUT12/SLC2A12 as a urate transporter that regulates the blood urate level in hyperuricemia model mice. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 117, 18175-7. 2020.
- J. Boocock et al., Genomic dissection of 43 serum urate-associated loci provides multiple insights into molecular mechanisms of urate control. Hum. Mol. Genet. 29, 923-43. 2020.
- 日本痛風・尿酸核酸学会. 尿酸値が低い方のための診療ガイドラインの解説. (公益財団法人 日本医療機能評価機構, 2019).
- 中山昌喜, 中嶌真由子, 松尾洋孝, 患者教育実践講座 腎性低尿酸血症のアスリートに対する患者教育. 高尿酸血症と痛風 27, 157-60. 2019.
- 中山昌喜, 医務室での使用に適した医療費計算ファイルの開発. 防衛衛生 66, 1-7. 2019.
- A. Nakayama et al., Clinical practice guideline for renal hypouricemia (1st edition). Hum. Cell 32, 83-7. 2019.
- M. Nakatochi et al., Genome-wide meta-analysis identifies multiple novel loci associated with serum uric acid levels in Japanese individuals. Commun. Biol. 2, 115. 2019.
- Y. Kawamura et al., Genome-wide association study revealed novel loci which aggravate asymptomatic hyperuricaemia into gout. Ann. Rheum. Dis. 78, 1430-7. 2019.
- N. Dalbeth et al., Gout. Nat. Rev. Dis. Primers 5, 69. 2019.
- Y. Toyoda et al., Functional characterization of clinically-relevant rare variants in ABCG2 identified in a gout and hyperuricemia cohort. Cells 8. 2019.
- 日本痛風・核酸代謝学会, 腎性低尿酸血症診療ガイドライン(第1版). 痛風と核酸代謝 42, 1-51. 2018.
- 中山昌喜 et al., 「腎性低尿酸血症診療ガイドライン」(第1版)の策定 痛風と核酸代謝 42, 1-6. 2018.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, 四ノ宮成祥, 尿酸値は低くても問題 日本人に多い「腎性低尿酸血症」とは? Medical Technology 46, 302-3. 2018.
- 四ノ宮成祥 et al., 腎性低尿酸血症診療ガイドライン(第1版). 痛風と核酸代謝 42, 1-51. 2018.
- T. Takada et al., Identification of ABCG2 as an exporter of uremic toxin indoxyl sulfate in mice and as a crucial factor influencing CKD progression. Sci. Rep. 8, 11147. 2018.
- M. Sakiyama et al., Common variant of BCAS3 is associated with gout risk in Japanese population: the first replication study after gout GWAS in Han Chinese. BMC Med. Genet. 19, 96. 2018.
- T. Higashino et al., A common variant of MAF/c-MAF, transcriptional factor gene in the kidney, is associated with gout susceptibility. Hum. Cell 31, 10-3. 2018.
- Y. Tashiro et al., Effects of osthol isolated from cnidium monnieri fruit on urate transporter 1. Molecules 23, 2837. 2018.
- 日本痛風・核酸代謝学会, 腎性低尿酸血症診療ガイドライン(第1版). (メディカルレビュー, 大阪, 2017).
- 中山昌喜, 松尾洋孝, 四ノ宮成祥, 【高尿酸血症-基礎・臨床の最新知見-】腎性低尿酸血症診療ガイドライン. 日本臨床 75, 1930-5. 2017.
- 山口聡 et al., 腎性低尿酸血症診療ガイドライン 尿路結石症と運動後急性腎障害の合併症について. 日本尿路結石症学会誌 16, 137-40. 2017.
- M. Sakiyama et al., Independent effects of ADH1B and ALDH2 common dysfunctional variants on gout risk. Sci. Rep. 7, 2500. 2017.
- H. Ogata et al., Meta-analysis confirms an association between gout and a common variant of LRRC16A locus. Mod. Rheumatol. 27, 553-5. 2017.
- A. Nakayama et al., GWAS of clinically defined gout and subtypes identifies multiple susceptibility loci that include urate transporter genes. Ann. Rheum. Dis. 76, 869-77. 2017.
- T. Higashino et al., Multiple common and rare variants of ABCG2 cause gout. RMD Open 3, e000464. 2017.
- Y. Yasutake et al., Uric acid ameliorates indomethacin-induced enteropathy in mice through its antioxidant activity. J. Gastroenterol. Hepatol. 32, 1839-45. 2017.
- B. Stiburkova et al., Functional non-synonymous variants of ABCG2 and gout risk. Rheumatology (Oxford). 56, 1982-92. 2017.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, 四ノ宮成祥, トランスレーショナルリサーチへの誘い(第3回) 尿酸異常症の遺伝子発見から腎性低尿酸血症診療ガイドライン策定まで. 尿酸と血糖 2, 43-6. 2016.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, 【高尿酸血症の最新トピックス】 臓器障害を考えたときの治療 尿酸トランスポーターを標的とする新規薬物の可能性. Modern Physician 36, 248-53. 2016.
- H. Yokokawa et al., Association between serum uric acid levels/hyperuricemia and hypertension among 85,286 Japanese Workers. J Clin Hypertens (Greenwich) 18, 53-9. 2016.
- M. Sakiyama et al., The effects of URAT1/SLC22A12 nonfunctional variants,R90H and W258X, on serum uric acid levels and gout/hyperuricemia progression. Sci. Rep. 6, 20148. 2016.
- M. Sakiyama et al., Identification of rs671, a common variant of ALDH2, as a gout susceptibility locus. Sci. Rep. 6, 25360. 2016.
- M. Sakiyama et al., Expression of a human NPT1/SLC17A1 missense variant which increases urate export. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 35, 536-42. 2016.
- H. Matsuo et al., Genome-wide association study of clinically defined gout identifies multiple risk loci and its association with clinical subtypes. Ann. Rheum. Dis. 75, 652-9. 2016.
- H. Matsuo et al., Hyperuricemia in acute gastroenteritis is caused by decreased urate excretion via ABCG2. Sci. Rep. 6, 31003. 2016.
- T. Higashino et al., Common variant of PDZ domain containing 1 (PDZK1) gene is associated with gout susceptibility: A replication study and meta-analysis in Japanese population. Drug Metab. Pharmacokinet. 31, 464-6. 2016.
- Y. Honkura et al., NRF2 is a key target for prevention of noise-induced hearing loss by reducing oxidative damage of cochlea. Sci. Rep. 6, 19329. 2016.
- H. Miyata et al., Identification of febuxostat as a new strong ABCG2 inhibitor: potential applications and risks in clinical situations. Front Pharmacol 7, 518. 2016.
- H. Domoto et al., Up-regulation of antioxidant proteins in the plasma proteome during saturation diving: unique coincidence under hypobaric hypoxia. PLoS ONE 11, e0163804. 2016.
- 中山昌喜, 藤田真敬, 妻鳥元太郎, 立花正一, in より効率的で安全な患者搬送を目指して, 立花正一, 編集. (所沢, 2015), chap. 3, pp. 70-81.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, 市田公美, 腎性低尿酸血症とその原因、対策. 最新医学 別冊 高尿酸血症・痛風 (最新醫學社, 大阪, 2015), vol. 診断と治療のABCシリーズ, pp. 99-106.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, ABCG2遺伝子変異という遺伝要因は環境要因よりも影響力が大きい. 高尿酸血症と痛風 23, 94. 2015.
- 中山昌喜, in えんご. (一般財団法人自衛隊援護協会, 東京, 2015), pp. 2-.
- M. Taniguchi et al., Carrier frequency of the GJB2 mutations that cause hereditary hearing loss in the Japanese population. J. Hum. Genet. 60, 613-7. 2015.
- H. Matsuo et al., ABCG2 variant has opposing effects on onset ages of Parkinson's disease and gout. Ann. Clin. Transl. Neurol. 2, 302-6. 2015.
- T. Chiba et al., Common variant of ALPK1 is not associated with gout: a replication study. Hum. Cell 28, 1-4. 2015.
- T. Chiba et al., NPT1/SLC17A1 is a renal urate exporter in humans and its common gain-of-function variant decreases the risk of renal underexcretion gout. Arthritis Rheumatol. 67, 281-7. 2015.
- J. Furukawa et al., Functional identification of SLC43A3 as an equilibrative nucleobase transporter involved in purine salvage in mammals. Sci. Rep. 5, 15057. 2015.
- T. Kawate et al., High levels of DJ-1 protein and isoelectric point 6.3 isoform in sera of breast cancer patients. Cancer Sci 106, 938-43. 2015.
- 中山昌喜, 藤田真敬, 妻鳥元太郎, 立花正一, ヘリによる硫黄島への急患搬送の実際 自験例における教訓と工夫について. 防衛衛生 61, 155-62. 2014.
- 高田雄三 et al., 痛風・高尿酸血症のリスク評価のための迅速遺伝子検査. DNA多型 22, 151-4. 2014.
- Y. Takada et al., Common variant of PDZK1, adaptor protein gene of urate transporters, is not associated with gout. J. Rheumatol. 41, 2330-1. 2014.
- T. Takada et al., ABCG2 dysfunction increases serum uric acid by decreased intestinal urate excretion. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 33, 275-81. 2014.
- M. Sakiyama et al., Ethnic differences in ATP-binding cassette transporter, sub-family G, member 2 (ABCG2/BCRP): genotype combinations and estimated functions. Drug Metab. Pharmacokinet. 29, 490-2. 2014.
- M. Sakiyama et al., A common variant of organic anion transporter 4 (OAT4/SLC22A11) gene is associated with renal underexcretion type gout. Drug Metab. Pharmacokinet. 29, 208-10. 2014.
- M. Sakiyama et al., Common variant of leucine-rich repeat-containing 16A (LRRC16A) gene is associated with gout susceptibility. Hum. Cell 27, 1-4. 2014.
- M. Sakiyama et al., Common variants of cGKII/PRKG2 are not associated with gout susceptibility. J. Rheumatol. 41, 1395-7. 2014.
- A. Nakayama et al., Common variants of a urate-associated gene LRP2 are not associated with gout susceptibility. Rheumatol. Int. 34, 473-6. 2014.
- A. Nakayama et al., Common dysfunctional variants of ABCG2 have stronger impact on hyperuricemia progression than typical environmental risk factors. Sci. Rep. 4, 5227. 2014.
- H. Matsuo et al., ABCG2 dysfunction increases the risk of renal overload hyperuricemia. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 33, 266-74. 2014.
- H. Matsuo et al., ABCG2 dysfunction causes hyperuricemia due to both renal urate underexcretion and renal urate overload. Sci. Rep. 4, 3755. 2014.
- T. Chiba et al., Identification of a hypouricemia patient with SLC2A9 R380W, a pathogenic mutation for renal hypouricemia type 2. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 33, 261-5. 2014.
- S. Suma et al., Associations between body mass index and serum uric acid levels in a Japanese population were significantly modified by LRP2 rs2544390. Nagoya J. Med. Sci. 76, 333-9. 2014.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, 高田龍平, 市田公美, 四ノ宮成祥, 【日本が貢献した世界的新知見】 ABCG2と高尿酸血症. 高尿酸血症と痛風 21, 43-8. 2013.
- 中山昌喜 et al., 国外訓練におけるインフルエンザ集団発生の診療経験と対策. 防衛衛生 60, 145-52. 2013.
- 高田雄三 et al., 全自動SNPタイピング装置を利用した痛風の遺伝子タイピング. DNA多型 21, 256-60. 2013.
- Y. Takada et al., ABCG2 SNP typing using HRM assay : Effective approach for gout and hyperuricemia risk evaluation. J. Clin. Welfare 10, 64-9. 2013.
- A. Nakayama et al., Common missense variant of monocarboxylate transporter 9 (MCT9/SLC16A9) gene is associated with renal overload gout, but not with all gout susceptibility. Hum. Cell 26, 133-6. 2013.
- H. Matsuo et al., Common dysfunctional variants in ABCG2 are a major cause of early-onset gout. Sci. Rep. 3, 2014. 2013.
- S. Takeuchi et al., Increased xCT expression correlates with tumor invasion and outcome in patients with glioblastomas. Neurosurgery 72, 33-41. 2013.
- Y. Hinohara et al., No association between MTHFR C677T and serum uric acid levels among Japanese with ABCG2 126QQ and SLC22A12 258WW. Nagoya J. Med. Sci. 75, 93-100. 2013.
- 中山昌喜, 松尾洋孝, 市田公美, 四ノ宮成祥, 【腎疾患治療マニュアル2012-13】 尿細管疾患 尿細管機能異常症 腎性低尿酸血症. 腎と透析 72, 370-3. 2012.
- 千葉俊周, 松尾洋孝, 中山昌喜, 市田公美, 四ノ宮成祥, XV 膜輸送系の異常 遺伝性腎性低尿酸血症. 別冊 日本臨床 (日本臨床社, 大阪, ed. 2, 2012), vol. 新領域別症候群シリーズ 20, pp. 807-11.
- 松尾洋孝, 市田公美, 高田龍平, 中山昌喜, 四ノ宮成祥, 尿酸動態の支配要因としての尿酸トランスポーター. 細胞工学 31, 553-7. 2012.
- 高田雄三 et al., High Resolution Melting法によるABCG2遺伝子のSNPタイピング. DNA多型 20, 286-90. 2012.
- S. Takeuchi et al., L-Leucine induces growth arrest and persistent ERK activation in glioma cells. Amino Acids 43, 717-24. 2012.
- N. Hamajima et al., Significant interaction between LRP2 rs2544390 in intron 1 and alcohol drinking for serum uric acid levels among a Japanese population. Gene 503, 131-6. 2012.
- K. Ichida et al., Decreased extra-renal urate excretion is a common cause of hyperuricemia. Nat. Commun. 3, 764. 2012.
<その他特記事項>
令和5(2023)年2月23日(木・祝)・24日(金)に第56回日本痛風・尿酸核酸学会総会(大会長:防衛医科大学校長 四ノ宮成祥)をホテルグランドヒル市ヶ谷(東京都新宿区)にて主催
https://procomu.jp/tsufu2023/