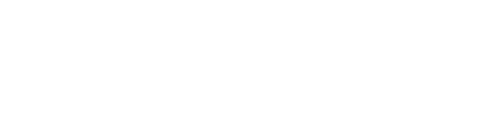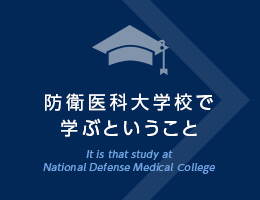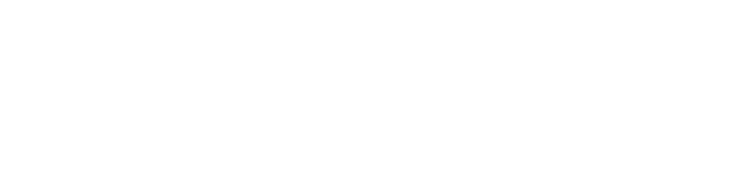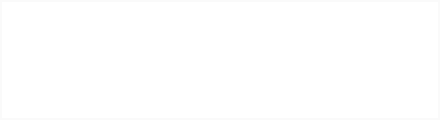臨床検査医学
(1)沿 革

令和4年11月10日 臨床検査医学講座スタッフ等
臨床検査医学講座は、昭和52年3月に米国ベイラー医科大学から着任した鈴木実教授が、基礎医学講座としての「病理学第一講座」を開講したことに始まる。平成6年4月に鳥潟親雄先生が第2代教授として着任し、その後、防衛医大副校長(教育担当)に昇格したため、平成10月4月に河合俊明助教授が第3代教授に昇任した。平成15年4月、防衛医大1期中西邦昭2等空佐がUC転官により当講座講師に着任、平成16年に助教授に昇任した。平成18年6月、当講座は臨床講座の「臨床検査医学講座、Department of Pathology and Laboratory Medicine」に移行した。平成19年11月、15期の緒方衝3等海佐が、UC転官で自衛隊横須賀病院から当講座助教に着任した。平成22年5月、中西准教授が防衛医大病院検査部副部長に転任、平成24年11月に緒方助教が講師に昇任した。平成26年4月、臨床検査医学講座教授が病院検査部長を兼務する新体制となり、中西准教授がその初代の教授・検査部長に昇格した。同年8月に緒方講師が病院検査部に転任し、平成28年10月、米国USUHSに留学中の土屋基裕医師(筑波大医学部卒、防衛医大29期相当)が当講座助教として着任した。平成29年10月、昇任した緒方准教授が検査部から当講座に転任となった。平成30年4月、27期宮居弘輔3等陸佐がUC転官で自衛隊中央病院(以下、中病)から当講座の助教に着任し、陸・海・空自からのUC転官者が揃った。平成30年6月、中西教授が第74回日本臨床検査医学会関東・甲信越支部例会を防衛医大にて主催した。中西教授の定年退官に伴い、平成31年4月、7期松熊晋技官が中病から第五代講座教授・第六代検査部長に就任し、現在に至っている。宮居助教は令和2年に学内講師に昇進したが、3年限定のUC転官制度のため、令和3年3月にCU転官で2等陸佐となって中病に異動した(1年後の令和4年4月に病院検査部講師に再UC転官)。令和3年4月、防衛医大26期桂田由佳2等陸佐がUC転官で防衛医大学生部から助教に着任した。令和5年2月現在、教授(検査部長兼務)1、准教授1、助教2で、教務職員として富永晋技官が剖検、教育・研究補助等の講座業務に携わっている。令和2年10月より、33期の松永絢乃3等陸佐が研究科学生として所属し、自衛隊入間病院から6期高橋央1等空尉、中病から41期栗原歩2等陸尉が通修し、研究や臨床検査専門医取得の研修等に励んでいる。
(2)教育業務の概要等
講座名が臨床検査医学講座となった当初、担当する教育はそれまでと同様、病態病理講座と分担した病理学の講義・実習だけだったが、平成26年から、臨床検査医学の講義・実習、クリニカルクラークシップ(BSL)等も加わった。近年、BSL時期の前倒し、アーリーエクスポージャー等の拡充も進み、医学科6年間を通したトータル教育のあり方が問われており、検査部ではなく臨床検査医学講座での課題と受け止めている。令和4年度には、医学科第3学年の学生たちに生前の画像、臨床検査値等の臨床所見を付与して病態を考察させ、課題発表と討議を行ったのち、検査値の読み方や剖検所見を解説する改変RCPC(reversed clinico-pathological conference)を開始した。この狙いは、本格的な臨床科目の履修に入る直前に、将来医師となる上で自分に何が足らないか、その後の臨床医学で何が修得されるべきか等々を学生たち自身が具体的に認識できる体験機会とすること、すなわち基礎医学と臨床医学の橋渡しである。その後、彼らは第4学年で輸血、血液等実習、研究室配属による剖検例等の症例研究、第5~6学年で検査部BSLを行うことになる。当講座の英語名に「Pathology」の名称が入っている職責を踏まえ、「病理学と臨床検査医学を融合させた教育」の実践が今も課題である。やる気のある研究室配属学生は英語論文の作成・投稿も行っており、実際、令和元年、令和2年、令和3年各々1個ずつの学生英語論文が掲載されている。看護学科にも、安全管理等を踏まえた臨床検査医学の講義等を行っている。
(3)研究の要約
中西教授時代まで、電子顕微鏡、組織化学、免疫組織化学、fluorescence in situ hybridization 、ELISA、Northern blotting、Southern blotting、Western blotting、polymerase chain reaction、共焦点レーザー顕微鏡等を駆使した肺・胸膜腫瘍、尿路系腫瘍の発生・予後等に関わる研究、腸管スピロヘータ症の研究等が行われてきた。現在も、これらの手法を踏襲しつつ、緒方准教授が腸管スピロヘータ症の研究を続行、桂田助教が病態病理講座の津田均教授のご指導の下、乳癌研究を推進するとともに、松永研究科学生を軸に、骨・軟部領域の研究が行われている。骨・軟部腫瘍は、未だ病態不明な部分が多く、近年は、EWSR1-SMAD3陽性線維芽細胞腫瘍、NTRK再構成紡錘形細胞腫瘍、EWSR1-nonETS融合を示す肉腫、BCOR関連肉腫等、融合遺伝子名が冠した腫瘍名が多く出現してきた反面、STAT6、H3.3G34W、SMARCB1、MDM2/CDK4、DDIT3等々、遺伝子変化を可視化できる免疫染色の発展も著しい。これらを踏まえ、検査部における骨軟部領域の外科病理診断に役立つ研究に、日夜努力している。
以下に、直近2年間の臨床検査医学講座スタッフ筆頭の出版英語論文を示す。
ア.Matsukuma S, et al. Lipomembranous fat necrosis: A distinctive and unique morphology (Review). Exp Ther Med 2022; 24: 759.
イ.Matsukuma S, et al. Histopathology of intraarticular loose body in view of the joint-related vasculature. Ann Vasc Med Res. 2022; 9: 1147.
ウ.Ogata S, et al. Mucosal eosinophilic infiltration may be a characteristic of human intestinal spirochetosis. BMC Infect Dis. 2021 21: 721. Doi: 10.1186/s12879-021-06418-8,