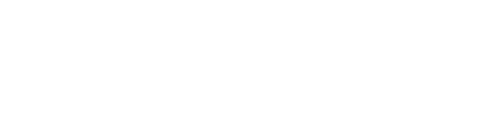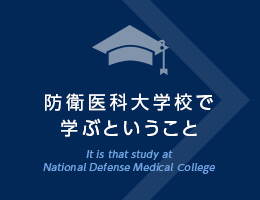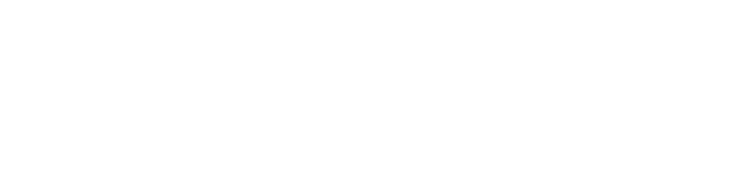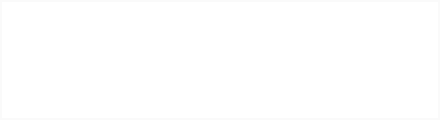衛生学公衆衛生学
沿革

衛生学公衆衛生学講座は本校の講座再編によって平成18年4月より旧衛生学および旧公衆衛生学講座が併合されたことによる新講座である。各々の経緯は、まず旧衛生学講座の初代教授に昭和49年に横堀栄教授が着任した。次いで、昭和57年に第2代教授に万木良平教授が昇任した。その後、平成2年に第3代教授として大野秀樹教授が着任し、平成12年に第4代教授として櫻井裕教授が着任した。
一方、旧公衆衛生学講座においては、初代教授として、昭和49年に阿部克己教授が着任した。次いで、昭和61年に中村健一教授が第2代教授として着任した。その後、平成2年に古野純典教授が第3代教授として着任し、平成8年に吉澤信行教授が第4代教授として着任した。吉澤教授の定年退官を機に両講座が併合され、平成18年4月に旧衛生学の櫻井教授が衛生学公衆衛生学講座の初代教授に就任した。平成28年4月、櫻井教授は副校長(教育担当)に就任し規定により教授職を離れ、平成29年4月に角田正史教授が第2代教授に就任した。
現在の本講座の構成人員は教授を含め5名の職員というコンパクトな構成であるが、研究科学生、事務スタッフを含め全員が一丸となって講座の運営、教育および研究に取り組んでいる。
本講座は、他大学の教授・准教授の輩出が多いことも特徴である。獨協医大の春木教授、名城大学の梅田教授、山形県立米沢栄養大学の大益教授、湘南鎌倉医療大学の眞鍋教授、杏林大学の片桐教授が本講座の出身である。
教育の概要
衛生学公衆衛生学講座では第3学年に対し、衛生学、公衆衛生学の講義および実習を行い、また第6学年における衛生学公衆衛生学の講義を担当している。衛生学および公衆衛生学の教育目標は集団の疾病予防と健康の維持・増進であり、その実践には、グローバルな健康事象の把握、科学的な疾病予防、健康増進の具体的方策の確立および行政施策の評価など多面的な活動が必要である。代々の教授の専門分野および社会情勢の変化に対応して教育の主眼点はその都度変遷してきたが、教育に対する基本姿勢は現在も引き継がれ、発展を続けている。
衛生学の講義では、予防医学概論、疫学、様々な分野における環境衛生学、産業衛生学など、広範な領域にわたって教育をおこなっている。また衛生学実習では学生に対し、実際の産業職場、ごみ処理場を見学させ、産業衛生学、環境衛生学の必要性を体感させている。
公衆衛生学の講義では、予防医学全体像を把握させ、社会医学の意味を理解させることを目的としている。その教育内容は保健統計、保健医療福祉関連法規と制度、国際保健、地域保健・地域医療、予防医学、医療安全管理、医療倫理等に多岐にわたっている。
公衆衛生学実習では、少人数のグループに分かれて産業保健・地域保健・国際保健・障害者保健・食品保健など学生自身が選択したテーマを事前学習した上で、該当施設を訪問し実地実習により現場を体験する。そしてグループ毎に各テーマの現状や今後の課題などを考察し、論文形式の報告書を作成できるように指導している。また報告書作成と共に、学会形式の発表討論会も実施し、実習で習得した知識を学生間で共有させている。事前学習と実地実習、そして事後の報告書作成や発表会を通して公衆衛生学の知識を確実にすることは、学生の社会医学系学習のモチベーション増大に繋がるものである。
第6学年の講義においては、新たに提起された衛生学と公衆衛生学上の問題点を理解させると共に衛生学と公衆衛生学を総括的に復習させ、その知識を確固たるものにさせる教育を行っている。
また、卒後研修として社会医学系専門医研修防衛医科大学校プログラムが令和4年10月に認可され、既に研修を開始している。また、日本医師会認定産業医講習を防衛医大医師会と共同して行っている。
研究活動
研究に関しては、1)自衛隊部隊、特に海上自衛隊の協力を得て、自衛隊員の健康管理的研究を大きな研究課題としている。防衛医大の任務として将来の医官育成があるが、卒業生と連携してビッグデータの解析を行い、隊員や医官に有益な結果を還元している。2)産業医学の分野の研究も主要な研究課題で、産業の現場をフィールドとして肥満や糖尿病等の疫学研究に取り組み、またメンタルヘルスに関する疫学研究を行っている。従来の個人を追う疫学研究に加え、事業所という単位で疾病発生を見る手法を試みている。さらに3)ゲノム編集技術、iPS細胞を用いた職業がん毒性機序の解明も行っている。これらの分野に加え以下の様々な分野の研究を行っている:4)ゲノム疫学、運動疫学などの研究(他講座と協力)、5)分子疫学アプローチによる輸血学などの研究、6)毒性学の研究について、動物実験を用い、環境汚染物質の神経毒性の評価、7)環境要因の健康リスクのコントロールを目指す疫学およびリスク評価研究である。これらの研究の成果は自衛隊のみならず社会全体の健康保持増進の一部として寄与できるものと考える。